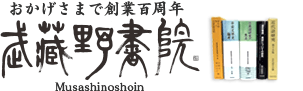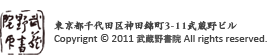ホーム > 書籍案内 > 話題の本(おすすめ) > 日本語の歴史 2 意志・無意志
注釈書・単行本など 詳細
日本語の歴史 2
意志・無意志
| 書名かな | にほんごのれきしに いし・むいし |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 柳田征司 著 |
| 著者(編者)名かな | やなぎだせいじ |
| ISBNコード | 978-4-8386-0429-6 |
| 本体価格 | 2,000円 |
| 税込価格 | 2,200円 |
| 判型 | 四六判並製カバー装 |
| 頁数 | 208頁 |
| 刊行日 | 2011年5月15日 |
| 在庫 | 在庫あり ※10冊以上購入ご希望の場合には別途ご連絡下さい。 |
それは、誰かが意識して行ったことなのか、それとも、自然に起きたことなのか。
現代の日本語は、その違いに鈍感になっているのだろうか?
現代の日本語は、その違いに鈍感になっているのだろうか?
はじめに
一 「修行者あひたり」
「修行者あひたり」型表現
助詞「に」を表していないのではないこと
「修行者あひたり」型表現とはどのような表現か
古代・中世日本語の「あふ」
逢魔・逢霊説
「相手が借りる」
意志形と無意志形とを分化させていない動詞「あふ」
無意志の出会いに用いられた「相手にあふ」
「修行者あひたり」型表現の衰退
二 「ある」(有) 「いる」(居) 「おる」(居)
「昔々おじいさんとおばあさんがありました」
「をり」の語源/「おる」と「いる」
南紀方言・八丈島方言の「ある」
先行研究
『竹取物語』の「あり」と「をり」
「ある」と「いる」「おる」
三 意志動詞「忘る」と無意志動詞「忘る」
有坂秀世氏が考えたこと
四段活用の「忘る」
四段活用動詞「忘る」の意味
下二段活用の「忘る」
忘れる内容が主格に立つ例―「我が面の忘れむしだは」
「父の写真」
大和の歌に見える忘れる内容が主格に立つ例
『今昔物語集』に忘れる内容が主格に立つ例は存するか
「忘る」の語源
「忘れかぬ」「忘れす」その他
有坂説が成り立つ可能性
忘れる内容がヲ格に立つ確かな例
四 「前車ノ覆スヲ見テ後車ノ誡ヲ知ル」
吉田澄夫氏の研究
亀井孝氏の指摘
『車馬』
第九二則の原拠
「覆ル」と「覆ス」
新古・文体差
「前車ノ覆ス」の表現価値
『今昔物語集』の「船俄ニ覆テ」「船打返シテ死ヌ」
「前車ノ覆ス」の衰退
五 意志動詞の無意志的用法
意志動詞の無意志的用法
意志動詞の無意志的用法はいつから見えるか
意志動詞の無意志的用法の内実
主語が為手でない場合
対応する無意志動詞が存するということ
意志動詞の無意志的用法の成立とその後
「~てしまう」
六 「家の子、郎等多く討たせ、馬の腹射させて、引退く」
強がり表現・負け惜しみ表現から使役表現の随順用法へ
使役表現の許容用法・随順用法の不足
使役表現の内実
意志動詞の無意志的用法
武士詞
七 「アイマチ」(過)
『史記抄』に見える「アイマチ」
『史記抄』に見える「アヤマチ」
『史記抄』の「アイマチ」と「アヤマチ」
その他の抄物に見える「アイマチ」
「アイマチノ高名」
その後の「アイマチ」
「アヤマツ」と「アヤマル」
キリシタン資料の「アヤマチ」と「アヤマリ」
八 意志動詞化・使役・無意志動詞化・受身
―「散らス」「知らセル」「思わレル」「降らレル」─
他動・使役・自発・受身の接尾語
奈良時代における「ス」(四段活用)
奈良時代における「シム」
奈良時代における「ス」(下二段活用)
自発・受身の「ユ」・「ル」
無意志動詞に付く「ユ」
意志動詞化・使役・無意志動詞化・受身
「ス」(四段活用)「ユ」「ル」の成立
「ス」(四段活用)「ユ」「ル」の接続
「ラユ」「ラル」の成立と「ル」「ラル」の定着
使役「ス」(下二段活用)の成立
平安時代における使役「サス」の成立
平安時代における肥大化接尾語「カス」の成立
なぜ「~カス」なのか
平安時代における「~シテ」と「~セテ」
室町時代における「~シテ」と「~セテ」
現代語の「ス」と「セル」
九 「はた迷惑の受身」
自発・可能・受身・尊敬
「はた迷惑の受身」とは
受身の類別
「迷惑」
「はた」
望ましくないことだけを表す受身は存するか
「迷惑」意識・「はた迷惑」意識
おわりに
あとがき