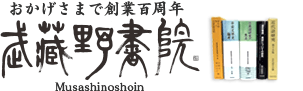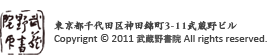ホーム > 書籍案内 > 話題の本(おすすめ) > 源氏物語の受容と生成
研究書(文学系) 詳細
源氏物語の受容と生成
| 書名かな | げんじものがたりのじゅようとせいせい |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 新美哲彦 著 |
| 著者(編者)名かな | にいみあきひこ |
| ISBNコード | 978-4-8386-0227-8 |
| 本体価格 | 12,000円 |
| 税込価格 | 13,200円 |
| 判型 | A5判上製函入カバー装 |
| 頁数 | 424頁 |
| 刊行日 | 2008年9月20日 |
| 在庫 | 品切れ中 |
第10回 2008年度 紫式部学術賞 授賞
序章
一 本文の流動性
二 物語の諸本
三 物語内容の差異
四 平安時代における『源氏物語』の書写
五 定家本・河内本の登場
六 定家本・河内本の相剋
七 本の権威化、中心と周辺
八 本書の構成
第一部 『源氏物語』本文系統の再構築
第一章 揺らぐ「青表紙本/青表紙本系」
一 はじめに
二 「青表紙本系」の問題
三 「青表紙本」という名称
四 「青表紙本」は「別本」か
五 定家の校訂
六 複数の定家作成『源氏物語』
七 おわりに
第二章 中世における源氏物語の本文
―了俊筆伊予切「夕顔」巻の本文系統―
―了俊筆伊予切「夕顔」巻の本文系統―
一 はじめに
二 了俊筆『源氏物語』
三 手法の紹介とデータ作成手順
四 分析結果
五 おわりに
第三章 『源氏物語』諸本分類試案
―「空蝉」巻から見える問題―
―「空蝉」巻から見える問題―
一 はじめに
二 手法と凡例
三 全体の分析結果
四 第一類(≒旧青表紙本系)の分析結果
五 おわりに
第二部『源氏物語』の本文世界
序節
第一章 賢木巻の本文世界素描(一)
―源氏をめぐる女君たち―
―源氏をめぐる女君たち―
一 はじめに
二 六条御息所母娘
三 朝顔斎院
四 朧月夜
五 おわりに
第二章 賢木巻の本文世界素描(二)
―苦悩する/したたかな藤壺―
―苦悩する/したたかな藤壺―
一 はじめに
二 桐壺院崩御
三 源氏と藤壺の密会
四 藤壺・源氏の出家願望
五 藤壺出家
六 藤壺出家後の源氏方
七 おわりに
第三章 絵合巻の本文世界素描―朱雀院の造型と絵―
一 はじめに
二 第二類(≒旧河内本系)における「絵」
三 朱雀院に寄り添う第二類(≒旧河内本系)
四 桐壺院の絵の行方
五 おわりに
第四章 絵合巻の物語絵合と源氏の造型―諸本文の差異から―
一 はじめに
二 物語絵合の勝負
三 源氏に寄り添う第一類(≒旧青表紙本系)
四 おわりに
第五章 本文の差異から読み解く源典侍
一 はじめに
二 本文の差異
三 おわりに
結節
第三部 『源氏物語』の享受
第一章 『光源氏物語抄』から『河海抄』へ―注の継承と流通―
一 はじめに
二 『光源氏物語抄』から『河海抄』へ
三 『河海抄』の引用方法
四 『河海抄』の『光源氏物語抄』引用
五 『光源氏物語抄』の流通経路
六 おわりに
第二章 今川了俊筆『源氏物語』について
―注記の性格と古筆家の改装―
―注記の性格と古筆家の改装―
一 はじめに
二 空蝉巻について
三 奥書の模写と古筆家
四 朱と墨の判別
五 了俊注の特徴
六 先行注からの影響
七 傍注注記者
八 おわりに
第三章 近世前期の写本製作
―伝三条西実枝筆『源氏物語』表紙裏反故から―
―伝三条西実枝筆『源氏物語』表紙裏反故から―
一 はじめに
二 当該『源氏物語』の製作年次
三 表紙裏反故の性質
四 反故を出した書肆について
五 表紙屋弥兵衛の製作する本
六 紙の種類と値段
七 作業の種類と値段
八 書写者について
九 おわりに
資料編
一 専修大学図書館蔵今川了俊筆『源氏物語』空蝉巻
二 今川了俊筆『源氏物語』桐壺・夕顔巻伊予切集成
三 伝三条西実枝筆『源氏物語』の表紙裏反故
―翻刻と紹介・文学資料篇―
―翻刻と紹介・文学資料篇―
四 伝三条西実枝筆『源氏物語』の表紙裏反故
―翻刻と紹介・雑記篇―
―翻刻と紹介・雑記篇―
初出一覧
あとがき
索引凡例