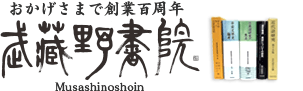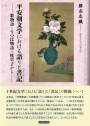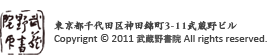ホーム > 書籍案内 > 話題の本(おすすめ) > 平安朝文学における語りと書記
研究書(文学系) 詳細
平安朝文学における語りと書記
―歌物語・うつほ物語・枕草子から―
| 書名かな | へいあんちょうぶんがくにおけるかたりとえくりちゅーる―うたものがたり・うつほものがたり・まくらのそうしから― |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 勝亦志織 著 |
| 著者(編者)名かな | かつまたしおり |
| ISBNコード | 978-4-8386-0776-1 |
| 本体価格 | 10,000円 |
| 税込価格 | 11,000円 |
| 判型 | A5判上製カバー装 |
| 頁数 | 276頁 |
| 刊行日 | 2023年3月3日 |
| 在庫 | 有り |
凡 例
序章 十世紀文学における「語り」と「書記」の
問題について
第一篇
第一章 『伊勢物語』における「語り」の問題
はじめに
一 初段における「語り」
二 二条后章段における「語り」
三 第九段から東国章段における「語り」
おわりに
第二章 『大和物語』における〈記録〉の方法
はじめに
一 元良親王をめぐる物語
二 斎宮をめぐる恋
三 三条右大臣の女御をめぐる恋
四 記録された「歌語り」
おわりに
第三章 『大和物語』における桂の皇女関連章段採録の意図
はじめに
一 『大和物語』に登場する皇女
二 桂の皇女について
三 柔子内親王と君子内親王の描かれ方について
おわりに─書き記された桂の皇女─
第四章 『大和物語』柔子内親王関連章段における
「省筆」について
はじめに
一 柔子内親王について
二 柔子内親王関連章段について
三 『大和物語』における省筆
おわりに
第二篇
第一章 『うつほ物語』における和歌と歌物語性
─藤原兼雅の例から─
はじめに
一 『うつほ物語』の和歌─全体像をみる─
二 俊蔭巻における兼雅の歌物語
三 あて宮求婚譚における兼雅と和歌
四 一条殿の女性たちと兼雅の歌物語
おわりに
第二章 『うつほ物語』における音楽性とエクリチュール
─「語り手」の存在と「会話文」「絵解」─
はじめに
一 『うつほ物語』における会話文の先行研究
二 「会話」・「和歌」の声と音楽
三 『うつほ物語』の語りと〈絵解〉
おわりに
第三章 『うつほ物語』「内侍のかみ」巻における朱雀帝・
仁寿殿の女御の〈対話〉
はじめに
一 帝の対話を引き受ける存在─仁寿殿の女御の意味─
二 帝の語りⅠ─仁寿殿の女御の手紙をめぐって─
三 帝の語りⅡ─仲忠とあて宮をめぐって─
おわりに
第四章 和歌を「書きつく」ことが示す関係性
─『うつほ物語』から『源氏物語』へ─
はじめに
一 歌集における「書きつく」
二 歌物語における「書きつく」
三 『うつほ物語』における「書きつく」
四 『源氏物語』の「書きつく」
─「扇」に書き付けられた贈答歌─
おわりに
第三篇
第一章 『枕草子』における中宮定子の
「語り」と「書記」一
─「清涼殿の丑寅の隅の」章段から─
はじめに
一 定子の「語り」①─和歌改変をめぐって─
二 定子の「語り」②─古今集暗誦をめぐって─
三 「語り」が書記される場としての『枕草子』
─「歌語り」と関わって─
おわりに
第二章 『枕草子』における中宮定子の
「語り」と「書記」二
─「殿などのおはしまさで後」章段から─
はじめに
一 章段前半における定子と清少納言
二 定子の「語り」が示すもの
三 定子の語りを受け止める清少納言
おわりに
第三章 『枕草子』雪山の章段における〈聖〉と〈俗〉
はじめに
一 常陸の介の聖俗
二 斎院および卯槌の聖性
三 雪山のゆくえ
四 明示されない和歌と語りの問題
おわりに
初出一覧
あとがき
索 引