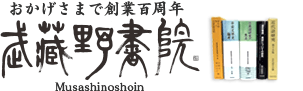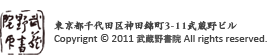ホーム > 書籍案内 > 話題の本(おすすめ) > 演能空間の詩学
注釈書・単行本など 詳細
演能空間の詩学
―〈名〉を得ること、もしくは「演技する身体」のパフォーマティブ―
| 書名かな | えんのうくうかんのしがく―なをえること、もしくは「えんぎするからだ」のぱふぉーまてぃぶ |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 深沢 徹 著 |
| 著者(編者)名かな | ふかざわとおる |
| ISBNコード | 978-4-8386-1005-1 |
| 本体価格 | 3,000円 |
| 税込価格 | 3,300円 |
| 判型 | 四六判並製カバー装 |
| 頁数 | 326頁 |
| 刊行日 | 2023年3月20日 |
| 在庫 | 有り |
はじめに─名前をめぐる問い─
第Ⅰ章 問題の所在
─テキストの「内」と「外」、もしくは『紫式部
日記』に見る自己言及表現の行為遂行機能─
一 「こそあど」構文のパフォーマティブ
二 編纂の果実としての『紫式部日記』
三 人称表現のパフォーマンス
四 「ちょうつがい」としての自己言及
五 メタ・フィクション論の地平
六 西洋リアリズム演劇と「第四の壁」
第Ⅱ章 真実から三番目に遠く離れて
─「源氏能」に見る、「歓待」の
作法としての「名指し」と「名告り」─
問題の所在
─「ウソ」に「ウソ」を重ねたまがいもの?
一 「歓待」の作法としての固有名への呼びかけ
二 「源氏能」の諸相
(夕顔、半蔀、葵上、野宮、須磨源氏、住吉詣、
玉鬘、浮舟、源氏供養)
三 〈他者〉の先行、あるいは対面的な〈場〉の
「二人称」
四 「ミメーシス」に「ミメーシス」を重ねるとは
どういうことか?
第Ⅲ章 はじめに「二人称」があった
─「第四の壁」のへだて、もしくは独我論の
くびきからの解き放たれ─
問題の所在─演劇の〈場〉における「作者」の〈死〉
一 パルマコンとしての「四人称」
二 演劇のことばのアイロニー
三 「事実をもって語らせる」ことなどできるのか?
四 演劇の〈場〉における人称表現の多面的複合形態
第Ⅳ章 かたらう「能」と、かたどる「狂言」
─演能の〈場〉における、「アイ(間)」の
はたらきをめぐって─
問題の所在─かたどりVSかたらい
一 主客二元論のくびき
二 熱くうたう「能」、あるいは〈同化〉の眩惑
三 〈異化〉の覚醒、あるいは冷たくかたる「狂言」
四 アレゴリーと異化効果
付論 「義経もの」にみるアイ(間)の「かたり」の
諸相
(鞍馬天狗、烏帽子折、熊坂、橋弁慶、正尊、
船弁慶、二人静、安宅)
第Ⅴ章 きつねたちは、なにもので、どこからきて、
どこへいくのか?
─〈名〉を得ること、もしくは「演技する身体」
の行為遂行機能―
問題の所在─「固有名」の翻訳不可能性と、演劇の
〈場〉におけるその「再現」
一 都市伝説─幼年期のきつねたち
二 上書きされる系譜─「震旦きつね」の飛来
三 白魔術VS黒魔術─「天竺きつね」の到来
四 在地(ヒナ)との出会い(一)
─「玉藻の前」の場合
五 在地(ヒナ)との出会い(二)
─恨み「葛の葉」の場合
六 「演技する身体」の行為遂行機能
七 ミミクリ─変換装置としての『殺生石』、
そして『釣狐』
八 ミメーシス─変換装置としての『三輪』、
そして『翁』
終章 民主の〈かたり〉
─三谷邦明が源氏物語研究に遺したもの─
はじめに─抜き取られた「躾糸」
一 躾糸としての「固有名」
二 いくつもの可能世界を拓く「固有名」
三 架空(ニセ)の「固有名」のあつかいをめぐって
四 方法としての「カテゴリー・ミステイク」
五 三谷邦明における「形而上学」の復権
六 「躾糸」のパフォーマンス
初出一覧
あとがき─ヴァルター・ベンヤミンに導かれて─
人名(固有名)索引