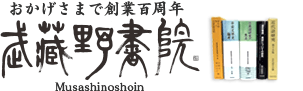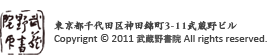ホーム > 書籍案内 > 研究書(語学系) > 小林賢次著作集 第二巻
研究書(語学系) 詳細
小林賢次著作集 第二巻
条件表現・否定表現・反語表現
| 書名かな | こばやしけんじちょさくしゅう だいにかん じょうけんひょうげん・ひていひょうげん・はんごひょうげん |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 小林千草 編 賢草日本語研究会 監修 |
| 著者(編者)名かな | こばやしちぐさ へん けんそうにほんごけんきゅうかい かんしゅう |
| ISBNコード | 978-4-8386-0809-6 |
| 本体価格 | 10,000円 |
| 税込価格 | 11,000円 |
| 判型 | A5判上製カバー装 |
| 頁数 | 318頁 |
| 刊行日 | 2025年8月20日 |
| 在庫 | 有り |
『小林賢次著作集』全六巻刊行 第二弾
本書は『小林賢次著作集』第二巻として、日本語における条件表現・否定表現・反語表現に関する論考を集めたものである。
うち、条件表現は、著作集第一巻を補うもので、〝条件表現の地理的分布と史的変遷〟などに目を向けたものを含む。 ――編者 小林千草
目 次
凡例
第一部 条件表現
第一章 条件表現史にみる文法化の過程
一 はじめに
二 順接条件の場合
三 逆接条件の場合
第一章 条件表現史にみる文法化の過程
一 はじめに
二 順接条件の場合
三 逆接条件の場合
四 接続助詞から接続詞へ
五 おわりに
第二章 完了性仮定と非完了性仮定の分類について
─補説・大蔵虎明本の「タラバ」─
一 はじめに
二 条件表現の分類について
三 完了性仮定と非完了性仮定について
四 おわりに
第三章 順接の接続助詞「ト」再考
─狂言台本にみる近代語条件表現の流れ─
一 はじめに
二 近世前期噺本の状況
三 狂言台本における「ト」の様相
四 同時・即時的表現から条件表現の形式へ
五 おわりに
第四章 確定条件の表現形式の地理的分布と史的変遷
五 おわりに
第二章 完了性仮定と非完了性仮定の分類について
─補説・大蔵虎明本の「タラバ」─
一 はじめに
二 条件表現の分類について
三 完了性仮定と非完了性仮定について
四 おわりに
第三章 順接の接続助詞「ト」再考
─狂言台本にみる近代語条件表現の流れ─
一 はじめに
二 近世前期噺本の状況
三 狂言台本における「ト」の様相
四 同時・即時的表現から条件表現の形式へ
五 おわりに
第四章 確定条件の表現形式の地理的分布と史的変遷
一 はじめに
二 「から」と「ので」に対応する表現形式
三 史的変遷とのかかわり
三・一 「サカイ」系の語の歴史と分布
三・二 「カラ」の発達
三・三 「ケー」「ケン」の分布と語源
三・四 「デ」「ノデ」の発達
四 「けれども」と「のに」に対応する表現形式
五 おわりに
第五章 仮定条件の表現形式の地理的分布と史的変遷
第五章 仮定条件の表現形式の地理的分布と史的変遷
一 はじめに
二 『方言文法全国地図』第三集の項目
三 完了性仮定・非完了性仮定の表現形式
四 形容詞の仮定形
五 おわりに
第六章 『浮世風呂』におけるト・バ・タラ
一 はじめに
二 近世後期江戸語における「ト」とその周辺
三 『浮世風呂』におけるト・バ・タラ
三・一 偶然確定条件〈a用語〉の場合
三・二 仮定条件〈b用法〉の場合
三・三 恒常条件〈c用語〉の場合
四 おわりに
第七章 森鷗外『舞姫』における条件表現
─近代文語文の読解と文法指導─
一 はじめに
二 「已然形+バ」の用法
三 「未然形+バ」の用法
四 おわりに
第Ⅱ部 否定表現
第八章 否定表現の変遷
─「あらず」から「なし」への
交替現象について─
交替現象について─
一 はじめに
二 「あり」「なし」の機能と分類
三 上代・中古における「あらず」「なし」の用法
四 中古和文資料における補助用言「なし」の検討
五 中世の変遷過程
五・一 説話集・軍記物語・歌論書等において
五・二 抄物・キリシタン文献・狂言台本において
六 おわりに
第九章 「ゴザナイ」と「ゴザラヌ」、「オリナイ」と
「オリャラヌ」「オヂャラヌ」
「オリャラヌ」「オヂャラヌ」
─その消長と待遇法─
一 従来の研究と問題点
二 「御座アル」「御座ナイ」の成立と発達
三 「ゴザナイ」から「ゴザラヌ」へ
四 「オリャル」「オヂャル」の否定形式について
第十章 院政・鎌倉時代におけるジ・マジ・ベカラズ
第十章 院政・鎌倉時代におけるジ・マジ・ベカラズ
一 はじめに
二 「ジ」「マジ」「ベカラズ」の分布
三 活用形をめぐって
四 表現内容をめぐって
五 「ジ」の固定化について
六 おわりに
第十一章 院政・鎌倉時代における否定推量・否定意志の
表現
─ジ・マジ・ベカラズの周辺─
一 はじめに
二 ジ・マジ・ベカラズ(補遺)
三 ザラム・ナカラム
四 ザルベシ・ナカルベシ
五 ベク…アラズ・ベク…ナシ
六 ベキ(事)ニ…アラズ〔~ナラズ〕
七 ベシト……ズ、その他
八 おわりに
第十二章 「ベシトモ覚エズ」考
一 はじめに
二 中古における「ベシトモ覚エズ」型表現
三 「ムト……思ハズ」などの表現
四 鎌倉時代における「ベシトモ覚エズ」型表現
五 おわりに
第十三章 室町時代における否定推量・否定意志の表現
一 はじめに
二 各表現形式の使用状況の概観
三 謡曲・幸若舞曲の場合
三・一 ジとマジ
三・二 マジの活用形と諸用法
三・三 ベカラズ、ベシト……ズなど
四 キリシタン文献・狂言台本の場合
四・一 ジの衰退
四・二 マジイとマイ
四・三 その他の表現形式
五 おわりに
第Ⅲ部 反語表現
第十四章 反語表現における文語性と口語性
─元和卯月本謡曲と大蔵虎明本狂言とを
比較して─
一 はじめに
二 肯定的事態の反語表現
二・一 〔A〕疑問詞〔+カ(ハ)〕……ベキ、
……ベキカ、など
二・二 〔B〕疑問詞〔+カ(ハ)〕……ム、
……メヤ、など
二・三 〔C〕疑問詞……ウ、疑問詞……ウゾ、
……ウカ、など
二・四 〔D〕〔省略・吸収〕表現、……モノカ、
……カ、など
三 否定的事態の反語表現
三・一 〔E〕疑問詞〔+カ〕……ナカルベキ、
疑問詞〔+カ(ハ)〕……ザルベキ、など
三・二 〔F〕疑問詞〔+カ(ハ)〕……ザラム、
疑問詞+カ……ナカラム、など
三・三 〔G〕疑問詞……マイゾ、……マイカ
三・四 〔H〕疑問詞+カ(ハ)……ザル、
疑問詞〔+カ(ハ)〕……ヌ、
疑問詞〔+カ(ハ)〕……ヌ、
……ナキカ、……ズヤ、……ヌカ、など
四 おわりに
引用・参照文献
小林賢次自筆書き入れより(編者の解説を含む)
所収論文の掲載書籍・雑誌一覧(第二巻)
本書所収の論文解説と未来への展望
編者のことば
賢草日本語研究会より御礼のことば
凡 例
1 研究書として刊行されたもの(「初版本」と称する)を
根幹に、既発表論文を研究テーマごとに巻を分けて構成
している。
2 初版本の論文体裁を尊重しており、編者の統一は、
【注】表示のあり方など、ごくわずかである。
【注】表示のあり方など、ごくわずかである。
3 編者の統一を控えた理由は、三〇~四〇年にわたる研究論
文執筆において、論題や扱う資料によってその文体や表示
面に変容が生じるのは自然の流れであると考えられるから
である。また、機械的な統一によって、その論文本来のも
つ〝調和〟をそこないたくなかったからでもある(ただ
し、数字の表記方法など最低限の統一については、読みや
すさを考慮し、編集部のほうで手を加えた箇所がある)。
4 小林賢次は縦書き派であったので、横書き(横組み)で出
版された一部の論考については、縦書きに直している。
5 引用・参照文献の挙げ方にも、古いものと新しいものとで
は変容が生じているが、初出、あるいは、初版本のままを
反映している
(ただし、編集部のほうで可能な限り形式の整理をおこな
った)。
6 初版本に小林賢次自筆の書き入れがあるものについては、
「小林賢次自筆書き入れより」という一項目を設けて、参
考に供する。
7 初版本に誤植等、すでに小林賢次によって朱が入っている
ものは、6の扱いをせず、訂正された形を本文上に反映さ
せている。