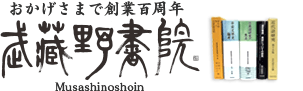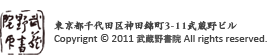ホーム > 書籍案内 > 研究書(語学系) > キリシタン資料を視点とする中世国語の研究
研究書(語学系) 詳細
キリシタン資料を視点とする中世国語の研究
| 書名かな | きりしたんしりょうをしてんとするちゅうせいこくごのけんきゅう |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 菅原範夫 著 |
| 著者(編者)名かな | すがわらのりお |
| ISBNコード | 978-4-8386-0192-9 |
| 本体価格 | 15,000円 |
| 税込価格 | 16,500円 |
| 判型 | A5判上製函入 |
| 頁数 | 464頁 |
| 刊行日 | 2000年6月30日 |
| 在庫 | 残部僅少 |
序文
序章
序章
第一章 平仮名表記の規範
第一節 室町時代の平仮名資料に見られる
一表記法─入声音─促音表記を中心として─
第二節 大蔵流狂言資料に見られる平仮名用字法の諸相
第一節 室町時代の平仮名資料に見られる
一表記法─入声音─促音表記を中心として─
第二節 大蔵流狂言資料に見られる平仮名用字法の諸相
第二章 表記に反映した筆記者の特性
第一節 梅沢本に見られる『栄花物語』の成立
─転写の様相─表記─音便形の特徴を中心にして─
第二節 『日葡辞書』の引用文におけるローマ字綴りの
改変について
第三節 キリシタン版ローマ字資料の表記と読み
─ローマ字翻字者との関係から─
第四節 国立国会図書館蔵古活字版『伊曽保物語』における
文字使用の二部性
第五節 まとめ
第一節 梅沢本に見られる『栄花物語』の成立
─転写の様相─表記─音便形の特徴を中心にして─
第二節 『日葡辞書』の引用文におけるローマ字綴りの
改変について
第三節 キリシタン版ローマ字資料の表記と読み
─ローマ字翻字者との関係から─
第四節 国立国会図書館蔵古活字版『伊曽保物語』における
文字使用の二部性
第五節 まとめ
第三章 『平家物語』の接続詞とその継承
第一節 延慶本『平家物語』の接続詞
第二節 延慶本『平家物語』の地の文の展開
―接続詞の用法に注目して―
第三節 覚一本『平家物語』の接続詞
第四節 天草版『平家物語』の接続詞
第一節 延慶本『平家物語』の接続詞
第二節 延慶本『平家物語』の地の文の展開
―接続詞の用法に注目して―
第三節 覚一本『平家物語』の接続詞
第四節 天草版『平家物語』の接続詞
第五節 まとめ
第四章 推量表現の変遷
第一節 延慶本『平家物語』の「ムズ」
第二節 『太平記』の推量表現
第三節 「うず」の消長
第五章 助詞と文章表現
第一節 『太平記』における希求─懇請の言い方について
─終助詞「かし」の用法を中心として─
第二節 キリシタン資料における終助詞「かし」
第三節 中止法的に用いられる助詞「し」
第六章 キリシタン資料における漢語
第一節『コンテムツス・ムンヂ』の漢語
第二節 天草版『平家物語』と原拠本の漢語
第七章 文献の性質と言語事象
第一節 『栄花物語』の口語的側面
第二節 古鈔本『宝物集』の文章構成とその文体
─最明寺本と書陵部本巻四部分とを中心にして─
第三節 『平家物語』の文末表現
─覚一本と延慶本との相違について─
第四節 まとめ
終章
既発表論文との関係
あとがき
索引
第一節 延慶本『平家物語』の「ムズ」
第二節 『太平記』の推量表現
第三節 「うず」の消長
第五章 助詞と文章表現
第一節 『太平記』における希求─懇請の言い方について
─終助詞「かし」の用法を中心として─
第二節 キリシタン資料における終助詞「かし」
第三節 中止法的に用いられる助詞「し」
第六章 キリシタン資料における漢語
第一節『コンテムツス・ムンヂ』の漢語
第二節 天草版『平家物語』と原拠本の漢語
第七章 文献の性質と言語事象
第一節 『栄花物語』の口語的側面
第二節 古鈔本『宝物集』の文章構成とその文体
─最明寺本と書陵部本巻四部分とを中心にして─
第三節 『平家物語』の文末表現
─覚一本と延慶本との相違について─
第四節 まとめ
終章
既発表論文との関係
あとがき
索引